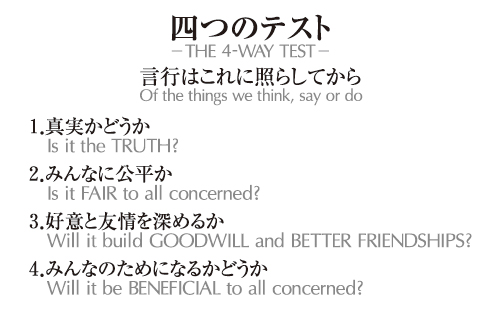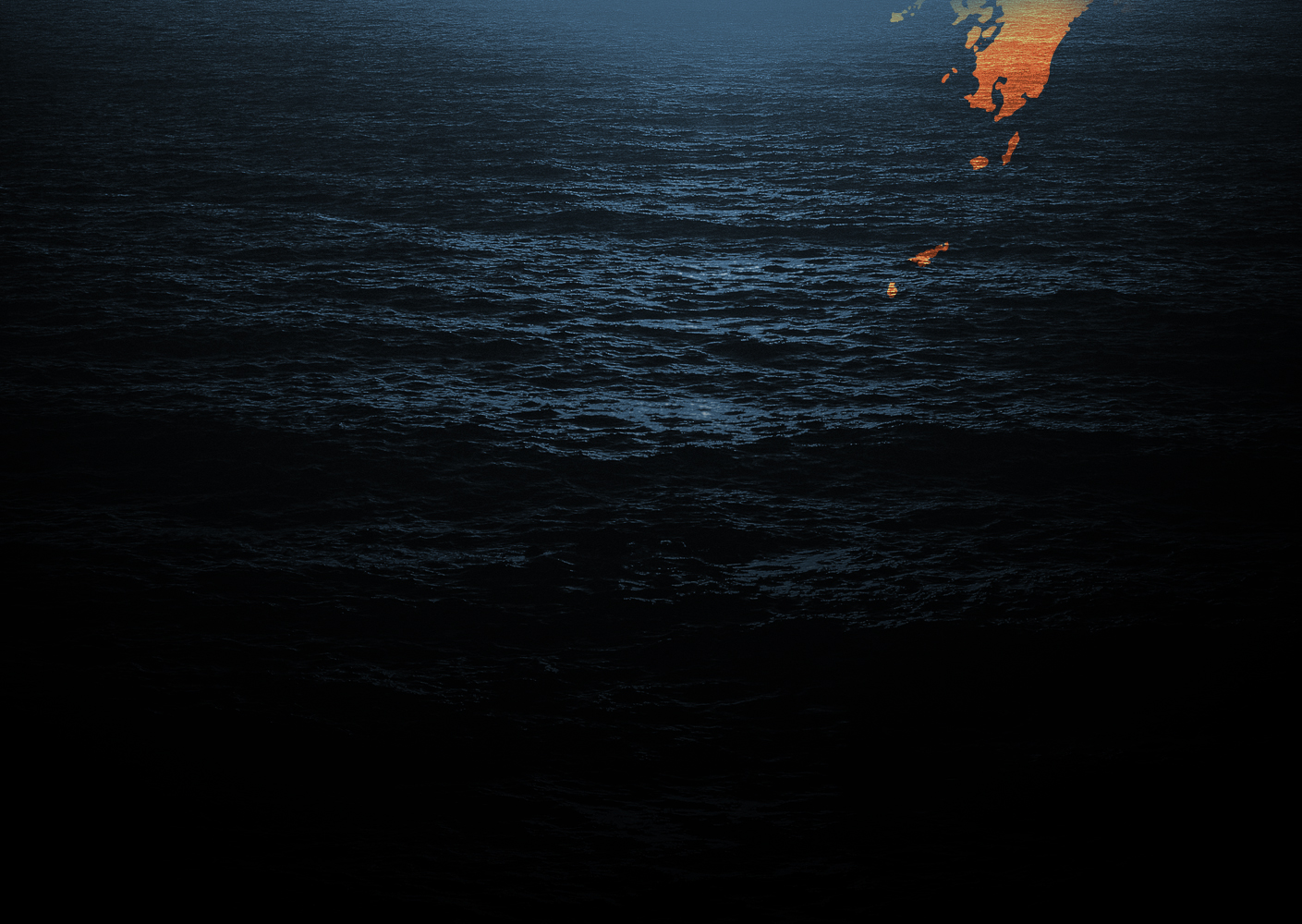「ロータリーの目的」
ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励し、これを育むことにある。具体的には、次の各項を奨励することにある。
1.知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること。
2.職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事は全て価値あるものと認識し、
社会に奉仕する機会としてロータリアン各自の職業を高潔なものにすること。
3.ロータリアン一人一人が、個人として、また事業および社会生活において、
日々、奉仕の理念を実践すること。
4.奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネットワークを通じて、国際理解、
親善、平和を推進すること。
付記
「ロータリーの目的」の4つの項目は、等しく重要な意味を持ち、また同時に行動を
おこさなければならないものであるということで、RI理事会の意見が一致した。
(ロータリー章典26.020)
2730ジャパンカレントロータリーEクラブ
2023-24年度 第21回(通算第398回)例会を開催いたします。
皆さまは気球に乗ったことがありますでしょうか。都城市は気球が身近な存在で、昔は家の近くを飛んでいることもありました。気球に熱風を送り込むバーナーの音が結構大きいので、近くに来ているとその音で気付くのです。
そんな昔は見ているだけの気球に乗る機会を得たのは、当社に気球クラブがあったからです。


写真は数年前に新しく買い替えた当社の気球です。
気球に地上からロープをつないで20mほど上がる「係留」は当社駐車場や高千穂牧場で搭乗体験イベントを開催したり、近隣の学校などから要請があった場合などに気球クラブが対応します。
気球は風の影響を大きく受けるので、晴れていても風が強いと上げることが出来なくなります。時間によっても風の状況は変わります。その為、搭乗体験イベントを予定していても、当日になって出来なくなる、或いは例えば100名の搭乗を予定していても、80名までで後の人が搭乗出来なくなってしまうということもあるのです。
搭乗する「かご」が大きくはないので、1回に乗れる人数が少ないのも難しいところです。バーナーの燃料となるボンベとフライトするパイロット、それ以外では子供で4~5名、大人で2~3名しか乗れません。スペースの問題と、重量制限もあるからです。その為、気球クラブのメンバーでパイロット免許を取る為にかなりのダイエットをした社員も居ります。パイロットが太っていると、搭乗可能人数が減ってしまいますので。。。

当社駐車場横の芝生広場で行われた係留体験で、上から写真を撮ったものです。
ローターアクトクラブ現役時代、クラブの35周年記念イベントとして、この気球搭乗体験を企画していたのですが、天候に恵まれず、参加者に気球に搭乗して頂くことが出来なかったのは残念な思い出です。。。
そんな係留体験とは別に、フリーフライトがあります。これは上空数百メートルまで上がります。
気球は、バルーン部分を折りたたんでかごの中に入れています。そのかごを車に積み下ろしするだけでも結構な重量なので人手が要るのですが、バルーンを広げてかごと繋ぎ、強力な扇風機で風を送り込んである程度膨らませてから、バーナーで熱風を送り込むことでバルーン部分が浮き上がります。また、フライトは飛ぶ高さを調整することで風向きが変わり、行先も変わります。出発地点がゴールではないのです。その為、フライトするメンバーと地上で待機するメンバーに分かれます。フライトして着地点を決めたら、地上で待機しているメンバーに連絡し、着地点で合流することになります。そして、今度はバルーンの空気を抜き、畳んでかごに入れ、車に乗せるという作業になります。気球を上げるには、4~5名は必要となります。
先述しました気球クラブのメンバーがパイロット免許を取る為に、フライト経験をしなければならない、でも、気球クラブのメンバーの都合が悪く人数が集まらないということで、何度か声がかかり乗せてもらったことがあります。
その時の写真です。





写真は同じ日のものではないので、晴れ具合が違いますが、この時で上空200~300メートル程まで上がっています。気球を上から見ると小さく見えますよね。

これは数年前の年末に9基飛んでいた時の写真ですが、写真では7基位しか分かりませんね。


こちらは今年の1月2日の画像です。通勤途中にたくさん飛んでいるのを見かけ、車を止められるとこまで行って途中で撮ったものと、会社の駐車場に着いてから撮ったものですが、広範囲で撮ろうとするとどうしても小さくなって分かりづらいですね。6基あるのが分かりますでしょうか。
このように、都城ではよく見かける気球ですが、それを広報手段として取り入れている企業は珍しいと思います。
ロータリークラブでもロータリーのこと、クラブのこと、そして奉仕活動など、テレビや新聞の取材、SNSへの投稿、チラシ配布など、様々な広報手段があります。誰をターゲットとするか、いかにインパクトを与えるか、より効果的な方法を皆さんと考えていきましょう。
2023-2024年度 第21回(通算第398回例会)幹事報告
なし
- (1)今後の予定
・2024年3月17日(日) 第3回理事会(鹿児島市内開催)
・2024年4月 7日(日) 鹿児島ポリオ撲滅募金事業
・2024年6月23日(日) 2730ジャパンカレントロータリーEクラブ10周年記念事業
- (1)小林RCシンポジュウムの開催について
・日 時:2024年2月4日(日)13:00~
・場 所:小林市文化会館
・参加者:今柳田
・登録料:無料
(2)2730地区RAC第51回地区年次大会について
・日 時:2024年3月2日(土)14:30~2024年3月3日(日)12:10
・場 所:宮崎観光ホテル
・参加者:今柳田、廣田、今福、吉永、柴田
・登録料:RC:23,000円(宿泊料含む)
(3)第36回全国ローターアクト研修会 山形大会について
・日 時:2024年3月23日(土)13:30~2024年3月24日(日)12:00
・場 所:(研修会)山形テルサ (懇親会)ホテルメトロポリタン山形
・対象者:RC、RAC、OB・OG
・登録料::12,000円(宿泊費別)
・その他:参加希望の方は1月26日(金)までに幹事へ連絡をお願いします。
(4)令和6年能登半島地震への支援について
・内 容:1月11日にメールで地区からの依頼文章を送付していますので確認ください。
・その他:寄付希望の方は幹事へ連絡をお願いします。
-
(1)宮崎県西部G第1回8クラブ合同会長幹事会
・日 時:2024年1月27日(土)10:30~
・場 所:地区事務所(メインホテル)
・参加者:吉永、今福
・内 容:地区行事について、各クラブの状況報告
例会プログラム計画が、各会員への配信されておりますので、
例会が滞りなく行われますように、例会プログラム委員会用のメールに
提出のご協力をお願いします。
①提出期限:例会日10日前
②提出先:SAA 宮本 健児
例会プログラム委員長 今柳田 幸代
③例会プログラム委員会メール:rec2730.reikai@gmail.com
① 他クラブの例会や行事でメークアップ補填
証明書や証明になる書類を添付して、補填する「例会回数」を連絡する。
② 自クラブの行事でのメークアップ補填
補填する「例会回数」を連絡する。
③ 報告先:幹 事 今福 修吾
副幹事 柴田 伸久 まで
なし
以 上
今週の例会は、月刊誌「致知」の代表取締役社長の藤尾秀昭さんが書かれた『プロの条件』という本について紹介させていただきます。
職業奉仕月間に関連して ~本の紹介~
例会プログラム委員長 今柳田幸代
私がこの本に出合ったのは、昨年度末です。今年3月に卒業予定の高等部3年生のA君が就職予定先の会社から「入社前に読んで感想文を提出するように」と課題として手渡された本の中にこの本がありました。A君は冬休み中に、感想文を書くことになりました。
学生としてゆっくりできる最後の冬休みに、作文が苦手なA君が頑張って書いてきた感想文は、拙いながらも自分が感じたことやこれから頑張りたいことなど、気持ちの伝わるものでした。A君が何に感動し、何を思ったのか、もっと知りたいと思い、私も課題の本を読んでみることにしました。
この本は、著者が社会に出て働きはじめた若い人たちに向け、活字の楽しさを知り、同時に人の生き方、人生について考えるきっかけをつかんでほしいという思いを込めて出版したものだそうです。
若い世代が働くことの原点をしっかりつかみ、そして働くことを通じてその道のプロになることはもちろん、人生のプロフェッショナルになってほしい、という願いを込め、拙著「小さな人生論」シリーズの中から、特に仕事に対する心構えに関するものを集めて収録したもののようです。
仕事を始める若者に向けた本ということもあり、読んでいて初心に返らせてもらえる内容でした。ぜひ会員の皆さんにもと思い、まとめました。すべての内容を書くことはできませんが、私の心に響いたことをいくつか紹介いたします。
まずは、「プロとアマの違いは?」という視点で4つのことをあげています。
第一は「自分で高い目標を立てられる人」、第二は「約束を守る」、第三は「準備する人」、第四は「進んで代償を支払おうという気持ちをもっている」です。第一、第二、第三は、すぐ想像でき納得したのですが、第四の「代償を支払おうという気持ち」とはどういうことだろうと感じました。著者は「プロであるためには高い能力が不可欠であり、高い能力を獲得するためには、時間とお金と努力を惜しまない、犠牲をいとわない、代償を悔いない。それがプロである。」述べてしています。
そして最後に、プロの共通した条件として「神は努力する者に必ず報いる、と心から信じている」ことをあげています。「不平や不満はそれにふさわしい現実しか呼び寄せないことを知り、感謝と報恩の心で生きようとする、それが“一流のプロ”に共通した条件である」と付け加え、「あなたはこれらの条件を満たしているだろうか、満たすべく努力しているだろうか」と問いかけていました。
これらの条件は簡単にクリアできるものではありませんが、大切なのは「意識して、努力している」ということなのかなと感じます。
次に、人が仕事を成就するために欠かせないものとして、「熱意」「誠意」「創意」の三つをあげられていました。
熱意について「熱意のないところには何事も生まれない。熱意、情熱こそ創造の源泉である。」と述べています。誠実について『誠は扇の要』の言葉を紹介し、「どんな才能、才覚、情熱があっても、誠実という要がなかったら、その人生は真の結実にいたることはできない」と述べ、『至誠神の如し』の言葉を紹介し、「誠心誠意を尽くすとき、人間業とは思えない、さながら神の仕業のようなことが出現する」と述べています。そして最後に、創意について「昨日よりは今日、今日よりは明日と常に前進するために、考え続ける。そこに仕事の飛躍が生まれる。」と述べ、「創意のもとになるのは教養であり、そこに人が勉強し、幅広い人間的教養を積んでいく意義と必要性がある」と述べています。
私も、どれだけ年齢を重ねても、熱い想いをもって、誠実に、現状に甘んじることなく、創意工夫できる、前進できる人でありたいと思います。
次に、一業を成した人に共通した要素として「価値を見いだす力」「信じる力」の二つのことをあげ、「価値を見いだす力。その価値を信じる力。これこそが信念の力である」と述べ、「信じ念じる力が道のないところに道をつくり、人を偉大な高みに押し上げていく」とも述べています。
自分が見いだした価値を信じぬくことは、簡単なことではないと思います。自分の信じ、貫き通す強さも必要なのではなかと感じました。
最後の章では、人生をひらくということについて書いており、人生をひらく鍵を三つ、心構えを四つあげています。
人生をひらく第一の鍵は「心をひらき、心を耕す」ことであると書いています。「ひらく」には、開拓する、耕す、という意味があり、「いかに上質な土壌もコンクリートのように固まっていては、良い種を蒔いても実りを得ることはできない」と例えています。
そして、人生をひらいた人に共通した心構えとして、その一「物事を前向きに捉える」、その二「素直」、その三「感謝の念を忘れない」、その四「愚痴を言わない」の四つをあげています。
人生をひらく第二の鍵は、社会教育家の田中真澄さんの言葉を引用して「心構えとは、どんなに磨いても毎日ゼロになる能力である。毎朝歯を磨くように、心構えも毎朝磨き直さなければならない」と書いています。
人生をひらく第三の鍵を古典「大学」の一文を引用して「必ず忠信をもって之を得、嬌態をもって之を失う」と書いています。「まごころを尽くしてすれば何事も成功するが、反対におごり高ぶる態度ですれば必ず失敗する」ということでした。
自分の心構え、行動一つで人生は変えられる。自分の人生、おおいに楽しみ、夢をもって、切りひらいていきたいものだなと感じました。
長くなりましが、本の紹介と私個人の感想は以上です。
内容の抜粋ですので、十分に伝わらない部分があるかと思います。興味をもっていただけましたら、是非、本物をお読みください。なお、私の感想は個人的なものですので聞き流してください。余談ですが、著者が10代の子どもに向けて、同じように思いを込めて出版した本『心に響く小さな5つの物語』もあるそうです。次は、この本も読んでみたいと思っています。