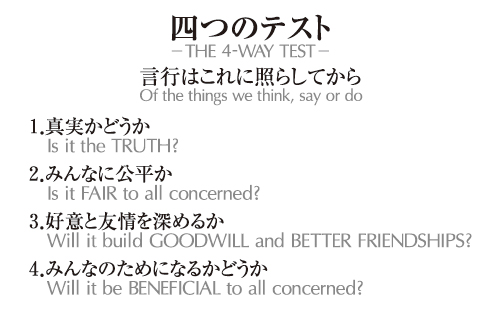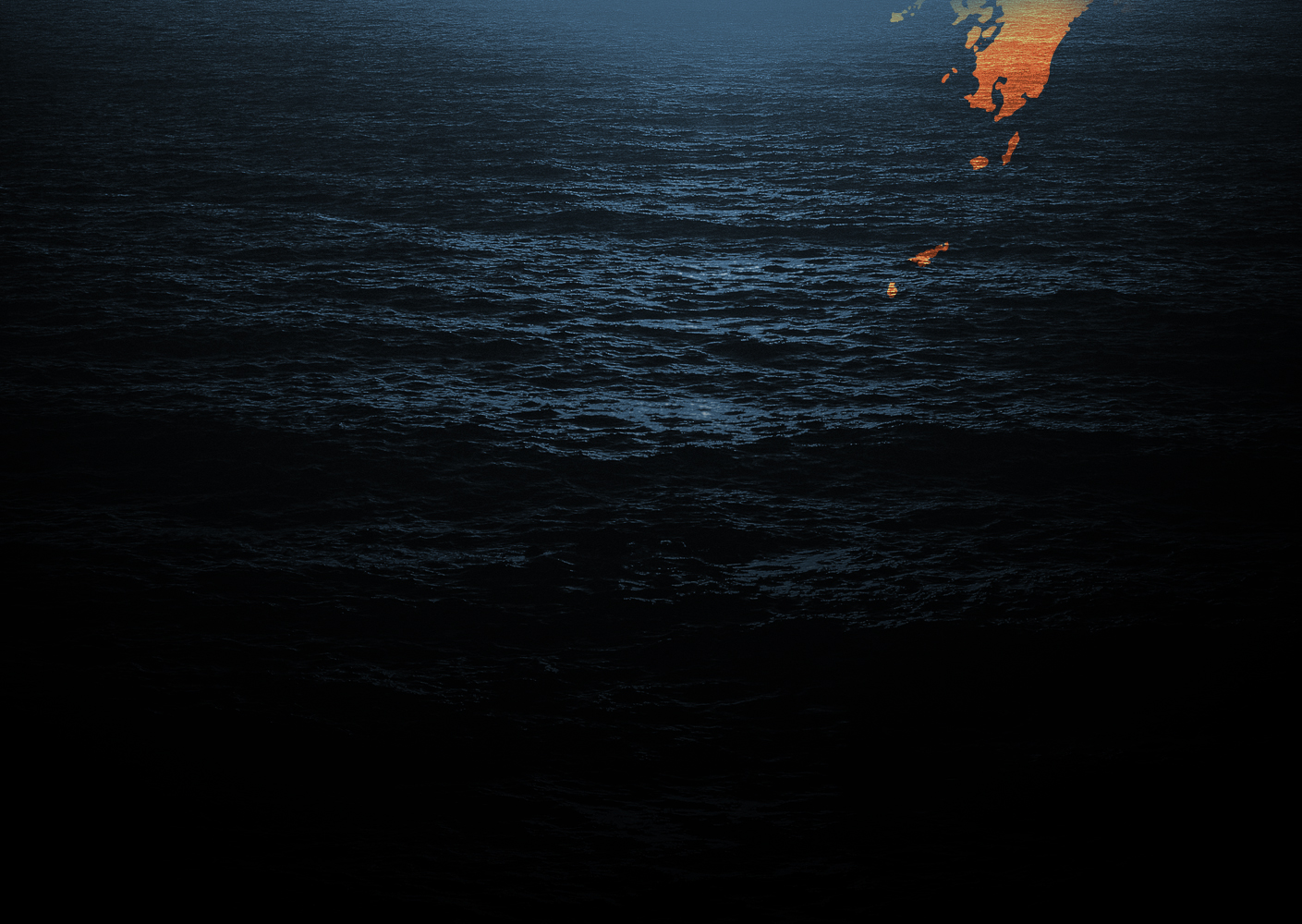国際ロータリーテーマ 「ロータリーは 世界をつなぐ」
RI2730 目 標 「クラブの活性化に努めよう」
2730ジャパンカレントロータリーEクラブの2019−2020年度第24回例会(通算244回例会)を開催いたします。
2月は「平和構築と紛争予防月間」です。「世界理解と平和週間(2月23日〜3月1日)」:1905年2月23日は、ロータリーの創始者・ポール・ハリスが友人3人と最初に会合をもった日です。この2月23日を祝う創立記念日は、「世界理解と平和の日」(World Understanding and Peace Day)として遵守されます。この日、各クラブは、国際理解、友情、平和へのロータリーの献身を特に認め、強調しなければなりません。理事会は、この2月23日に始まる1週間を「世界理解と平和週間」と呼び、ロータリーの奉仕活動を強調することを決議しています。(ロータリーの友より)
「貴島健一郎ガバナー挨拶」で『今年度の国際ロータリー会長は、米国アラバマ州のマーク・ダニエル・マローニー氏であり、会長テーマを「ロータリーは世界をつなぐ」と発表致しました。そこで私は、我が2730 地区の目標を「クラブの活性化に努めよう」と決定致しました』と言われて、年度後半に入りました。
世界経済フォーラム(WEF)の年次総会・ダボス会議が1月24日、4日間の日程を終えて閉幕しました。主要テーマの気候変動問題で各国要人や環境活動家との意見の違いを鮮明にしたようで、巨大IT企業に対するデジタル課税を巡っては、米国と欧州の対立の火種がくすぶり続けているようで、日本勢にとっては、会議での存在感の発揮が課題となった様で大手銀行や商社など多くの企業トップが参加したものの、海外メディアで発言が取り上げられる事は少なかった。報道ニュースで討論会に参加したサントリーホールディングス社長は「気候変動に対するプレゼンスをつくるのが、日本の課題だ」と指摘した。会場では飲み物容器に以前はペットボトルを利用していたが、ガラス瓶や色んな食器に自然に優しい物を利用する様に速いスピードで移行していくのではと思います。それと中国の「新型コロナウイルス」が感染者を増えて「春節連休」での人気渡航先のトップに日本を挙げていて、拡散防止に日本も対策してこれ以上広がらない事を祈ります。
総務省より「無線局免許手規則の一部を改定する省令案等の意見募集」が始まり、『アマチュア無線の免許手続きの簡素化、無資格者の利用機会の拡大および周波数の追加割当てについて』の件です。電波は世界中の「限り有る資源」で有る事でオリンピック・パラリンピック選手や応援などの観光者が来られます。指導者や引率者の連絡用に海外トランシーバーを利用する事で妨害電波が多くならない事を願って、総務省も国内規格トランシーバーで運用する事お願いしているが、電波は目に見えないので対策に苦悩している様です。
新年早々から世界も問題が多く、国際ロータリー会長テーマを思い考えてしまいます。
外部卓話
デフリンピックと私 尾塚愛実様(2017年トルコデフリンピック金メダリスト)
公共イメージ委員会委員長 東 岳也
今回の外部卓話をしていただくのは、尾塚愛実さん(22歳)です。
現在、京セラ(株)鹿児島川内工場に勤務し、デフバレーボール女子日本代表チームに所属されていらっしゃいます。
尾塚さんと最初に出会ったのは、彼女が小学校3年生の時、泳げない子の水泳教室の生徒として自分のクラスにやってきたのが最初です。
聴覚障がいを持っていらっしゃいますが、頑張り屋さんで、正直水泳教室の時は気が付かずに、今回お話しいただくデフリンピックで金メダルを取られた際に知りました。
2020年の今年は、オリンピック、パラリンピックのある年で、皆様も聞きなれた言葉であると思いますが、デフリンピックについては聞きなれない言葉であると思います。
デフリンピックとは聴覚障がい者を表す「デフ(Deaf)+オリンピック(Olympics)」の造語で「ろう者のオリンピック」という意味です。彼女は2017年の大会バレーの日本代表選手に選出され、見事金メダルを勝ち取った阿久根で初めての金メダリストでいらっしゃいます。
本日は、外部卓話として講師をお願いいたしました。現在彼女たちは、このデフリンピックに関してのクラウドファンディングにも挑戦されていらっしゃいます。
この機会にデフ競技に関心を持ち、ご協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。
■デフリンピックと私:尾塚愛実
皆様、はじめまして。尾塚愛実と申します。東さんとは、自分が小学生の時に通った水泳教室で出会いとっても鬼コーチでした。(笑)
 |
| 中央が尾塚愛実さん |
でも、休憩時間には、私たちを抱えて投げてくれるのがすごく楽しみでした。
今回SNSでクラウドファンディングの取り組みを始めたのをきっかけで、東さんから卓話のお話をいただきました。
ぜひ、私たちが活動しているデフリンピックについて、クラウドファンディングの取り組みについて知っていただければと思いますので、よろしくお願いします。
◆デフリンピックとは
聴覚障がい者を表す「デフ(Deaf)+オリンピック(Olympics)」の造語で「ろう者のオリンピック」という意味です。
 |
| 2017年トルコデフリンピック金メダル |
デフリンピックと他に、パラリンピックというオリンピックがありますが、どちらとも「障がいを持つ人のオリンピック」というイメージがありますが、中には、パラリンピックは聞いたことあるけど、デフリンピックって何?という人も多いと思います。
パラリンピックは、身体障がい者を対象とした障がい者スポーツの総合競技大会であって、オリンピック・パラリンピック・デフリンピックどれも4年に1度開催されます。
オリンピック・パラリンピックは同じ年に同じ国で開催されますが、デフリンピックは違う年に違う国で開催されています。また、メディアでの取り上げ方、認知度でも差があります。新聞では、パラリンピックはスポーツ面で扱われますが、デフリンピックは認知度も低いためか、社会面で扱いも小さく、デフリンピックの存在すらあまり知らない人が多いです。
デフアスリートもパラリンピックには「参加していない」ことも知られていません。
デフリンピックへの参加には、選手・スタッフとも自己負担が必要な状況です。
毎月1回、週末や連休を利用して各地方からメンバーが集まって代表チームの練習をしています。また、国からの支援も知名度もオリンピック・パラリンピックほどはなく、企業などのスポンサーも得にくいのが現状となっています。
私自身もデフバレーボール日本代表として2017年トルコで開催されたデフリンピックに初めて出場し、予選から決勝まで全7試合、1セットも落とすことなくストレートで勝ち続け、世界一、金メダルを獲得することが出来ました。
現在も、2020年7月世界選手権(開催国:イタリア)、2021年デフリンピック(開催国:ブラジル)2連覇を目標に月1回の遠征や地元での練習を頑張っています。
◆デフバレーとの出会い
私が、デフバレーボールを始めたのは高校卒業後。高校バレーの春高予選の時、日本デフバレーボールの理事長、監督さんが視察に来られ、デフバレーボールへ勧誘があり、1度、トライアウトで合宿に参加させてもらいました。高校までは健常の世界でバレーをしてきていたので、デフバレーボールという名前すらも自分でも知りませんでした。
初めてデフバレーボールの合宿に参加すると、私と同じように、聞こえない人たちが集まってバレーをしていました。聞こえない人たちだけのバレー競技もあるのかと驚き、デフバレーボールで、世界で戦ってみたいと夢が湧き、これまで健常の世界でやってきたことを活かしてデフバレーボールでも更に頑張ってみようと思い転向しました。
◆通常のバレーでの思い
 |
| プレー中も様々なコミュニケーションでやり取りをします |
小学校から高校までは健常者と同じ環境で育ち、バレーボールも健常のチームでプレーをしていました。初めの頃は、チームメイトの声や、監督の話している内容が聞こえず、分からなかったりして困ったこともたくさんありましたが、周りの仲間たちが、フォローしてくれたり身振りや簡単なサインを使って指示を出してくれたりしていました。
耳が聞こえなくても、「目で見る・判断する」ことは出来ると思い、視野の範囲を広げるトレーニングも日々練習をしながら力を入れていました。
 |
| 音のないバレーの世界 |
そのおかげで、レシーブの連携が出来るようになったり、スパイクでも相手のブロックや穴が見えるようになったり、さらには、周りが自分を呼んでるのを、聞こえなくても、自分を呼んでるのか?と感じ、すぐに振り向けるようになったりと、色々と健常者と同じ環境にいても、聞こえなくても出来ることがたくさん増え、聞こえないという壁をあまり感じず、バレーに対して夢中になっていました。聞こえなくても、「やればできる」と私を強く、成長させてくれた、バレーボールやバレーボールに関わった全ての人に感謝しています。
◆デフバレーと通常のバレーの違い
ルールは全て同じです。
通常のバレーと違うことは、デフリンピックのルールとして、聴覚に障がいのある人は聴覚のレベルもそれぞれ違うので、みんな平等になるように、補聴器を外して全く聞こえない状態でプレーをしなければなりません。チームメイトの声、歓声、審判の笛の音、ボールをはじく音などが聞こえない状態でプレーをしています。
 |
| 応援してくれる家族はもちろん会場にはデフリンピック日本代表の全ての競技(サッカー、水泳、卓球、陸上等)のたくさんの方に応援いただきました。 |
また、チームで声に出してプレー、連携することは難しく、監督の指示も声では聞こえません。
私たちは声の代わりに手話・口話・手話通訳など様々な方法を使ってコミュニケーションをとったり、チームでアイコンタクトを取りながらプレーをしています。見る側からすると、聞こえない状態でプレーをするってどんな感じだろう。ぶつかったり、繋がらなさそう。等、色々なイメージがあると思います。
聴覚障がい者はただ、「耳が聞こえない」というだけで、プレーや技術、実力は健常者並で、プロのバレーボールチームのように、スピードのあるコンビやパワフルなプレーも出来てそこまで大きな差はありません。
◆クラウドファンディング
このクラウドファンディングには、前回デフリンピック(2017年 トルコ)のデフバレーボールのムービーも掲載しておりますので、1度ご覧頂けると有難いです。シェアのご協力をして頂けるだけでも大きな力となります。
URL:
www.spportunity.com/tokyo/team/327/invest/432/detail/
今回、このような機会をいただきありがとうございました。皆さまからのご支援、ご協力のほどよろしくお願いいたします。