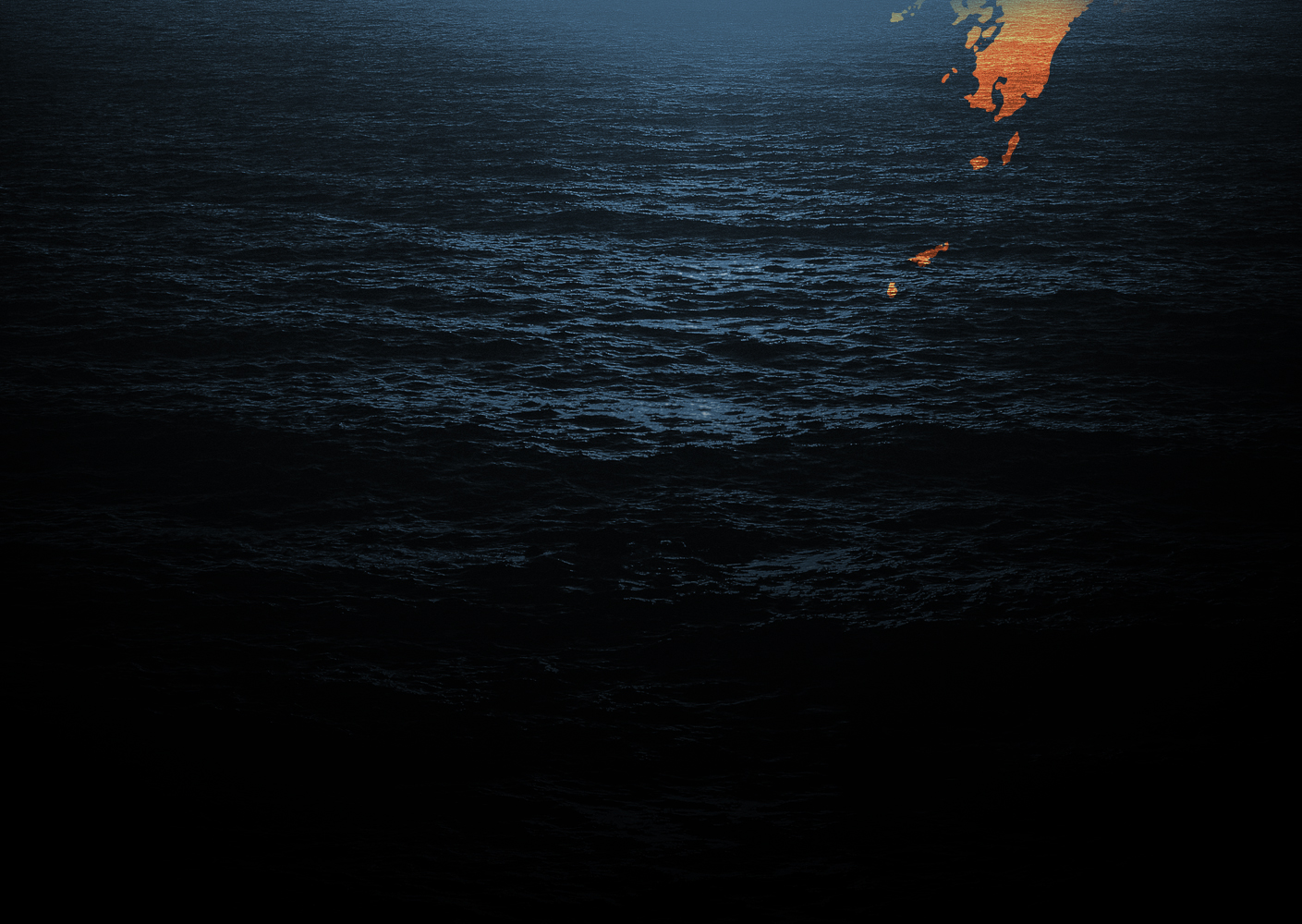2018-19年度 会長テーマ
「 Amazing Rotary (びっくりするようなロータリーに)」
みなさん,こんにちは。
2730ジャパンカレントロータリーEクラブ第28回例会を開催いたします。
3月は「水と衛生月間」です。きれいな水を利用できることは基本的な人権です。しかし世界には,適切な衛生設備が利用できない人が25億人と,安全な飲み水が得られない人が7億4800万人おり,さらに毎日1400人の子どもが,劣悪な衛生環境と不衛生な水を原因とする病気で命を落としています。
国連は2015年,環境と気候変動に対応しながら貧困問題と福祉改善に取り組むために,「持続可能な開発目標」を設定しました。目標の一つは水と衛生に関する項目で,「すべての人に水と衛生へのアクセスと持続可能な管理を確保する」ことを目的としています。
日本人は,「水と安全はただ」と言う程,水に困ることはあまりありません。私の勤務する学校でも,子どもたちは,普通に水道の水を飲んでいます。しかし,世界には,水を汲みに行くため学校に行けない子どもや,学校に行けても衛生的な水を飲めない子どもが多くいます。
ロータリーでも,井戸や雨水貯水システムの設置,水設備管理の研修,疾病予防のための水・設備の提供など,水関連の多くの活動が実施されています。以下にロータリーによる活動をご
紹介します。
.png)
当地区では,2017年度,3000地区よりグローバル補助金を利用してインドの小学校にトイレ,手洗い場と浄水器の設置依頼があり,これを引き受けました。トイレ,手洗い,飲料水は衛生上最も基本で重要なことです。また,鹿児島ロータリークラブは,1995年度にバングラディッシュにポンプ式井戸・簡易トイレ建設を行っています。
ポカラ・ロータリークラブ(ネパール)は,農村地域では水を得るために毎日25kmを歩かなければならず,水運びをしなければならない子どもも大勢いました。そこで,米国のウィリアムソン・ロータリークラブと協力して500人分の水を貯蔵できるタンクを設置しました。
.png)
大東ロータリークラブ(大阪)は,シティーマンガール(ネパール)にある学校の貯蔵タンク(12,000リットル)を活用するためのポンプとフィルターを設置し,年間を通じて安全な飲み水を供給できるようにしました。
700万人が水を原因とする疾病リスクにさらされているガーナでも,ロータリー会員は他団体と協力して,水と衛生プロジェクトを実施しています。
今月は,水のありがたさを改めて考えてみてはいかがでしょうか。
引用 ロータリーボイスHP,鹿児島ロータリークラブHP
「ロータリーの友を読んで」
会員増強維持委員長 池 海英
最近、人工知能(AI)をはじめ、情報技術は恐ろしいスピードで進化しております。2018年12月18日、アリババ・グループは中国杭州でアリババ無人ホテルをオープンして、AIが管理人になりました。宿泊の予約と部屋の選択はオンラインで行い、ホテル到着後は、高さ1メートルのロボットがホテルで接客します。宿泊客の個人情報はホテル内のすべてのエリアに共有され、顔認証技術で宿泊客の身元を確認し、サービスを提供します。
電子書籍の市場もこの数年間で急成長し、紙より携帯端末の画面で読書する現象が広がりつつあります。総販売額のほぼ半分を占めているアメリカは、市場規模の世界1位で、日本も2位についています。
その反面、紙の書籍の売り上げは世界的に減少傾向が続き、活字離れが加速しています。文化庁が2013年に調査した結果、1ヶ月に1冊も本を読まない人は47.5%もいました。新聞などの紙媒体は長らく不況状態だと言われています。
お恥ずかしい話で恐縮ですが、テレビ、バソコン、携帯、、、通信技術の発展とともに、私の読書量も段々減りました。
私は旧満州である中国吉林省延辺朝鮮族自治州で生まれ育ちました。照明灯以外の家電がない我が家に、珍しくラジオがやって来たのは、幼稚園生の時でした。電源を入れれば、小さい箱から人や動物や車などがいろんな声や音を出るのが、あまりにも不思議で、じっと中を覗いて見るのが日課でした。また運動が苦手で、本を読むのが大好きだったので、新しい本を手に入れられない時は、同じ本を暇つぶしに何回も読みました。我が家は私の小学生5年生の時にテレビを買って、その後は、洗濯機、炊飯器、冷蔵庫、、、毎回新しい家電が増えるのが本当に嬉しかった。
でも、テレビのニュースを見れば、世の中の出来事を分かるし、分からない単語や気になる記事はバソコンで検索すればいいし、おもしろいドラマもたくさん放送されて、一日があっという間で過ぎて、本を手にしてじっくり読むことが段々少なくなりました。
ロータリーEクラブに入会させていただいてからもう3年半が過ぎています。「ロータリーの友」はEクラブ入会してから、読めるようになりましたけど、毎回ネットで読もうとしたら、バソコンをわざわざ開いて読むのがなかなかできませんでした。このままならずっと読まないんだろうと思って、冊子を読むようにしました。確かに冊子を手に取ったら、ざっとでも目を通しました。
今回「ロータリーの友を読んで」を寄稿することになって、初めてゆっくり読んでみました。静かな部屋で、ページを開く音を出しながら、白い紙の上にある文字と鮮やかな写真にゆっくり目を通したら、思わず読書三昧だった時代が懐かしくなりました。また、国際と国内の社会実情、ロータリーのいろんな活動などを拝読し、たくさん勉強になって、素晴らしい冊子であることを改めて実感しました。常に丁寧に読んでいたら、もっと勉強になったのに、と深く反省しております。今さらですけれど、家にある「ロータリーの友」をもう一回読むことにしました。
アナログ時代に生まれた私は、やっぱり電子書籍より紙の書籍にもっと魅力を感じます。これを機会に、家でゆっくり紙の本を読む時間を少しずつ増やして、読書を楽しみたいです。
今後ともご指導よろしくお願いいたします。
ロータリーの友を読んで
直前会長 今福 修吾
例会プログラム委員会より表題のテーマをいただきましたので、先月発行された2019年2月号より、縦書きP4~P8に掲載されていた「21世紀世代の人生計画 地球と私の運命」と題された内容について触れたいと思います。
※この記事は、2018年3月31日に開催された「宮崎県西部分区IM基調講演」(講師 関西学院大学教授・日本国際連合学会事務局長 久木田 純 様)の内容をまとめられたものです。
この記事の中で、印象に残ったものが二点ありました。
一点目は、東ティモール民主共和国において、ポリオ撲滅ポスターでおなじみのジャッキー・チェン氏と一緒に取り組まれた「武術集団間の争いの仲裁」です。13の武術流派の争いを、ジャッキーと合同演武を行うことで和解に繋がり犯罪が減少したとの内容でした。
東ティモールは、インドネシアから独立後の混乱について度々報道を見ていましたが、そういえば最近見なくなったと思うとともに、平和に向かう一助として我らがジャッキーの活躍があったとの内容に感動しました。
二点目は、平和な世界の実現に向け世界の193か国が合意した「持続可能な開発目標[SDGs](“エスディージーズ”と読むそうです)」のお話しです。
SDGsとは、貧困や飢餓といった問題から働きがいや経済成長、気候変動に至るまで、21世紀の世界が抱える課題をについて、「だれひとり取り残さない」をスローガンとして世界193か国が合意したもので、2030年までに達成すべき17の目標と169のターゲット具体目標で構成されています。久木田講師は、“私たちのライフスタイルを含め、先進国自身が取り組む普遍的なもの”とお話しされています。
さて、“日本は先進国でありながら取り組みが遅れている”とのことでしたので、その取り組み状況について調べたところ、2018年7月に公表されたレポート(SDGsインデックス&ダッシュボード)での日本の達成度は「156か国中15位」でした。ちなみに、1位はスウェーデン、次にデンマーク、フィンランドと北欧諸国が並んでいます。
日本に対する主な評価は次の通りです。
(1)相対的に高い傾向となる評価項目
| № |
目 標 |
補足説明 |
| 目標1 |
貧困をなくそう |
|
| 目標3 |
すべての人に健康と福祉を |
|
| 目標4 |
質の高い教育をみんなに |
「このペースであれば達成予定」との評価 |
| 目標6 |
安全な水とトイレをみんなに |
|
| 目標7 |
エネルギーをみんなに そしてクリーンに |
|
| 目標8 |
働きがいも 経済成長も |
|
| 目標13 |
気候変動に具体的な対策を |
|
| 目標16 |
平和と公正をすべてのひとに |
|
(2)低い傾向と評価された項目
| № |
目 標 |
低い要因 |
| 目標5 |
ジェンダー平等を実現しよう |
女性国会議員の数や男女の賃金格差等 |
| 目標12 |
つくる責任 つかう責任 |
電子電気機器廃棄物の量等 |
| 目標14 |
海の豊かさを守ろう |
漁業活動の持続可能性等 |
| 目標15 |
陸の豊かさもまもろう |
種の保存リスク等 |
| 目標17 |
パートナーシップで目標を達成しよう |
実施手順の弱さ等 |
レポートには「特に高所得者層(先進国)が世界の中で果たすべき役割について考え行動することなしにはSDGsの達成は難しい。」との要約があり、久木田講師も講演の中で“日本は積極的に取り組んではいるが、全国的な広がりが遅れている。スピードを上げ、世界をリードする国になってほしい。”と話されています。また、講演の結びで久木田講師がお話しされた“私たち20世紀世代は、自ら持続可能なライフスタイルを実践し、次世代にバトンタッチする責任があります。一世紀を見渡して、人類の歴史に残る巧みなライフシフトをする時だと思います”との考えにとても共感しました。
ジャッキー・チェン氏はご存じの通りポリオ撲滅親善大使を務められ、講演を行われた久木田様はロータリー財団国際親善奨学生としてシンガポールに留学された経験をお持ちです。私たちのロータリークラブには世界で活躍されている方が数多くいるのだと再確認するとともに、私もロータリアンとして世界の平和と安定のための取り組みを少しずつではありますが継続的に実施していきたいと考えます。
(補足)
日本の「SDGs推進本部」はSDGs達成に資する優れた取り組みに貢献した企業・団体等を表彰していますが、昨年12月に開催された「第2回 ジャパンSDGsアワード」において、鹿児島県大崎町が「副本部長(内閣官房長官)賞」を受賞されました。詳細はインターネットで確認できますので、興味のある方は検索ください。
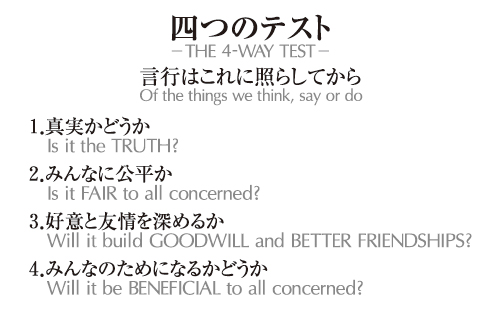

.png) 当地区では,2017年度,3000地区よりグローバル補助金を利用してインドの小学校にトイレ,手洗い場と浄水器の設置依頼があり,これを引き受けました。トイレ,手洗い,飲料水は衛生上最も基本で重要なことです。また,鹿児島ロータリークラブは,1995年度にバングラディッシュにポンプ式井戸・簡易トイレ建設を行っています。
当地区では,2017年度,3000地区よりグローバル補助金を利用してインドの小学校にトイレ,手洗い場と浄水器の設置依頼があり,これを引き受けました。トイレ,手洗い,飲料水は衛生上最も基本で重要なことです。また,鹿児島ロータリークラブは,1995年度にバングラディッシュにポンプ式井戸・簡易トイレ建設を行っています。.png) 大東ロータリークラブ(大阪)は,シティーマンガール(ネパール)にある学校の貯蔵タンク(12,000リットル)を活用するためのポンプとフィルターを設置し,年間を通じて安全な飲み水を供給できるようにしました。
大東ロータリークラブ(大阪)は,シティーマンガール(ネパール)にある学校の貯蔵タンク(12,000リットル)を活用するためのポンプとフィルターを設置し,年間を通じて安全な飲み水を供給できるようにしました。