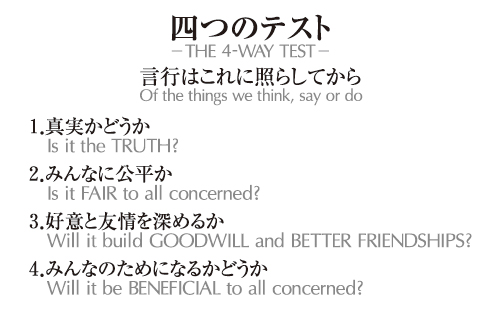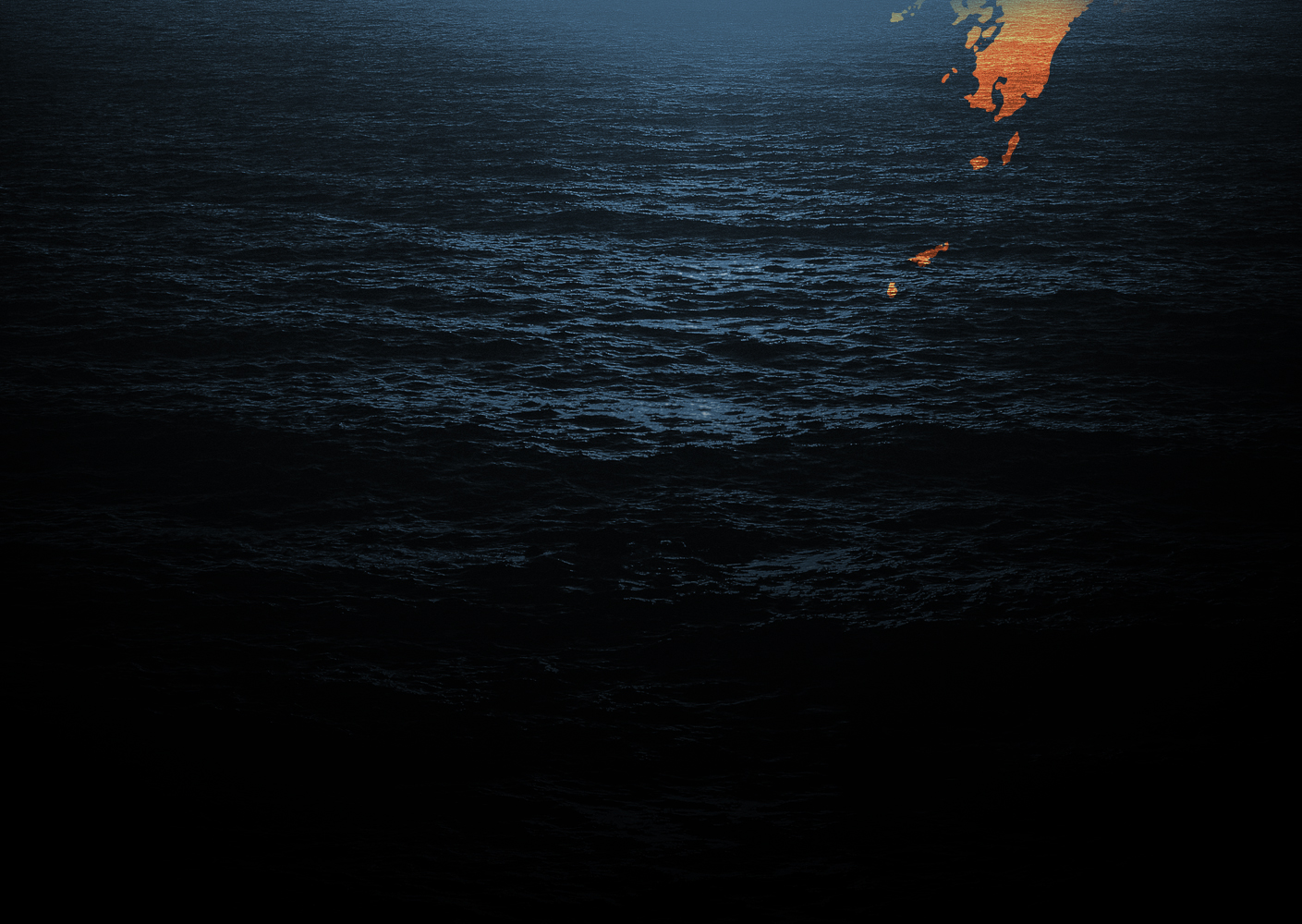新「ロータリーの目的」
ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励し、これを育むことにある。具体的には、次の各項を奨励することにある。
1.知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること。
2.職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事は全て価値あるものと認識し、社会に奉仕する機会としてロータリアン各自の職業を高潔なものにすること。
3.ロータリアン一人一人が、個人として、また事業および社会生活において、日々、奉仕の理念を実践すること。
4.奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネットワークを通じて、国際理解、親善、平和を推進すること。
付記
「ロータリーの目的」の4つの項目は、等しく重要な意味を持ち、また同時に行動をおこさなければならないものであるということで、RI理事会の意見が一致した(ロータリー章典26.020)
♪ 奉仕の理想 ♪
奉仕の理想に 集いし友よ
御国に捧げん 我等の生業
望むは世界の 久遠の平和
めぐる歯車 いや輝きて
永久に栄えよ
我等のロータリー ロータリー

♪ それでこそロータリー ♪
どこで会っても やあと言おうよ
見つけた時にゃ おいと呼ぼうよ
遠い時には 手を振り合おうよ
それでこそ ローロー ロータリー

♪ 手に手つないで ♪
手に手つないで つくる友の輪
輪に輪つないで つくる友垣
手に手 輪に輪 ひろがれまわれ
一つ心に おおロータリアン
おおロータリアン

♪ ありがとうロータリー ♪
富士の高嶺みつめて 地に足を踏みしめ
喜びと誇りを胸に 今もこれからも
ありがとうロータリー
出逢えた奇跡 奉仕の理想に向かって
ありがとうロータリー
分かち合うしあわせ
共に歩もう 未来をみつめて
それぞれのなりわいを それぞれの方法で
歩んできた だから今 新しい道がある
ありがとうロータリー
出逢えた奇跡 奉仕の喜びに向かって
ありがとうロータリー
分かち合うしあわせ
共に歩もう 未来をみつめて
ありがとうロータリー
出逢えた奇跡 奉仕の理想に向かって
ありがとうロータリー
分かち合うしあわせ
共に歩もう 未来をみつめて

みなさん、こんにちは。
2730ジャパンカレントロータリーEクラブ第24回例会を開催いたします。
先日、弊社で運営する飲食店を移転いたしました。今までは「ダーツ」というスポーツに特化したダーツバーとして運営しておりましたが、食事をメインとした「ダーツマシンも設置してあるダイニング形態」とし、席数も26席から90席へと大幅に拡大し、かなり思い切った形での業態転換を行いました。
その移転に伴いスタッフも大幅増員する必要があり、求人媒体に募集広告を掲載したり、口コミでの求人紹介等を行い、面接・採用・教育といった流れを日々行っている状態です。面接・採用については取締役が行いますが、教育については店長ならびに旧店舗から勤務してくれているスタッフに依頼をしています。実際の現場での業務、接客、そういったことを仕事をしながら学んでいただくようにしています。
その教育を任せている店長から、予想していなかった視点での報告がありました。
それは「いただきます」「ごちそうさま」が言えないスタッフがいるということです。
当社の店長は料理長も兼任しています。料理に対する思入れというものを強く持っています。そういった視点からなのかもしれませんが、スタッフ用に賄い料理を作った時に
・料理は出されたら暖かいうちに食べる。
・手を合わせて「いただきます」「ごちそうさま」を言う。
・食べ終わった皿は炊事場へ運ぶ。
これはスタッフでなくとも、家庭で教わっている最低限のマナーのはずなのに、そういった基本的なことが出来ていないというのです。
命を繋いでくれる食材への感謝、食材を料理してくれる人への感謝、そういった心が備わっていれば自然と出来るはずのことが、今の若いスタッフには備わっていないとのことでした。
仕事に関する教育ではないかもしれないが、人材育成の一環にはなるだろうと、そういった部分まで含めての教育を改めて店長に依頼するととともに、この際他にも気になる点はないか聞いてみました。
すると現時点で聞いたことはないが、スタッフに質問してみたいことがあるとのことでした。それは
「給料は誰からもらっているか?」という質問をしてみたいとのことでした。
店長が当社入社前に勤めていた居酒屋さんでスタッフに同じ質問をしたところ七割のスタッフはお客様と答え、三割のスタッフは会社・社長と答えたそうです。
社会人としての経験年数がそういった答えを導き出しているのかもしれませんが、経済の仕組み、感謝の心、そういったことを伝えていくのも社内での上席者の役割なのかもしれないね、という話になりました。
当社のスタッフは正社員よりもアルバイトの人数が多く在籍しております。学生も居れば、就職経験のある方、アルバイトしかしたことのない方もいらっしゃいます。多様な若いスタッフと接する機会が多いのは、今回店舗規模を拡大したことによりいただけた機会であり、若いスタッフの将来のための経験値を作るのは、店長や経営陣の使命なのかもしれません。
昔「今の若いモンは…」と言われていたはずの私がそういった立場になっていることに苦笑しながら、伝えられる限りの全てを伝えていきたいと思います。
ちなみに新店舗は鹿児島の繁華街、天文館の真ん中に位置しております。週二~三日は私も顔を出しておりますので遊びにきてください。
ポリオ街頭募金活動報告
奉仕プロジェクト委員長 中村 泉
開催日 2017年1月15日 11:30~14:30
開催場 宮崎イオンモール
参加者 菊池さん、桐明さん、戸高さん、西さん、宮本さん、今福さん、東さん、花里さん、吉永さん、
今柳田さん、無漏田さん、中村
奉仕プロジェクト委員会を中心に企画したポリオ街頭募金活動を宮崎イオンモールにて開催、無事終了しました。
当日は寒冷の為、天候に危惧しておりましたが、少し寒さを感じる程度で開催されました。
今回の活動はEクラブとして、財団100年記念事業の一つの意味合いもありました。参加者の大きな声での呼びかけ、風船配布にて、募金額32967円が集まりました。
募金者の中には、快く募金される方、親子で募金される方、まだ小学校にも通わないくらいの少女が1人で、首から下げた財布から募金する等、心温まる様子見ることがありました。
これもひとえにRCに対する御理解と参加者の協力で成功したと思います。ありがとうございました。


職業奉仕
ロータリー財団委員会 戸高 豊文
私は「職業奉仕」という言葉を、ロータリーに入って初めて知りました。会員になった後、さまざまな人々の意見を聞いてみても、正直、まだまだ深い理解には至っていません。今回「私の職業奉仕」というテーマをいただきましたのでネットでもいろいろと調べてみました。その中で「なるほど!」と思いことがあったので、最初にそのことについて書きます。世界でも超有名な人の話です。
その人はロータリークラブの始まる前の1901年に第1回ノーベル平和賞を受賞した方です。名前は「アンリ・デュナン(1828-1910)」・・皆さんの中にはこの人の名前をご存知の方もおられるでしょう。そうです。アンリ・デュナンは「赤十字」を作った人です。しかしこの人の生涯を読んでみると、次のようなことが書かれていました。
アンリ・デュナンが25歳の時、迫害を受けていた人たちを見て、「彼らとともに農場を開拓し、製粉会社をつくろう」という強い思いで、勤めていた銀行を辞め、製粉会社を設立します。しかし、奉仕活動の方に力を注ぐあまり、1858年(30歳)ごろから借金が増えていき、1865年には投資していたジュネーブ信託銀行が倒産してしまい、これが決定的な打撃となって、株主らから契約不履行で訴えられ、1867年(36歳)に破産宣告を受けます。その後のアンリ・デュナンには誰も見向きもしなくなり、世間からも忘れ去られていきます。1895年に長い間忘れ去られていたアンリ・デュナンをある新聞記者が「発見」して、かろうじて功績が再び脚光を浴びるようになるのです。
つまり、アンリ・デュナンは「奉仕活動に熱を入れすぎた余り自分の会社を潰した」ということになります。この話しには側面があって、ちょうどこの頃はフローレンス・ナイチンゲールの活躍した時期でもありますが、ナイチンゲールは「自己犠牲だけの奉仕は長続きしない。経済的基盤が必要だ」と主張し、アンリ・デュナンのがむしゃらな奉仕活動に反対しました。
私はこのエピソードから次のような教訓を得ました。
1)奉仕活動に熱を入れすぎると会社を破綻させる可能性がある。
2)自己犠牲だけの奉仕は長続きしない。経済的基盤が必要。
「奉仕活動をするには経済的基盤が必要」という当たり前といえば当たり前、深いといえば深い主張こそが、ひょっとしたらロータリーのいう「職業奉仕」の一面なのかもしれません。
ただ、アンリ・デュナンの一途な「少年のような」純粋さがなければ、今の赤十字は存在しないのであり、その足元にも及ばない私たちはどうしても金銭面を見てしまいます。ですからビジネスよりも奉仕にその軸足を置くぐらいの意識を持つことが必要ではないでしょうか。
さらに最近では奉仕活動を支える資金の捻出方法にはさまざまなものがあり、広く世間に知らせるための手段もたくさんあります。このような仕組みを利用して奉仕活動の経済的基盤を構築することもできます。
さて、私自身のことですが、私の職業分類は「NGO・NPO職員」となっています。私は宮崎県延岡市に本部がある、インド国際子ども村「ハッピーバリー」の事務局長をしていますので、その職業分類で参加させていただいています。しかし、この役職は無給で、何の報酬もいただいていません。ですから厳密には「職業ではない」のかもしれません。
一方、何で収入を得ているのかというと、私は「東証一部企業の正社員」なのです。この会社は企業向けのいわゆる経営者保険を販売する会社です。つまり、「右手で奉仕活動、左手で収入活動」というバランスのとれた生活をしています。
奉仕一辺倒でもなく、ビジネス一辺倒でもないという、この絶妙なバランスは私にとってはとても心地よいものです。奉仕活動をしている時、ビジネスで受ける心身のストレスも何となく軽減しているような気もします。
さらに、インドとの関わりの中で、自然に身についた英語やインターネットなどの技術、そして何よりも世界の人々と交わることで培われてきた「みずから進んで行動する精神」は、きっとロータリーの中で活躍できる場面があると思っています。
実は昨年末から年初にかけて、インターネット上では2つのロータリークラブの解散が伝えられました。アメリカとイギリスです。アメリカの例は創立76年のクラブです。しかし24名の会員の内、アクティブな会員は12名ほど、しかも平均年齢は78歳というのです。長年、会員の増強に努めてきたが集まらず、ついに断念したとの報道でした。
今の日本のロータリークラブは創立50年ほど、あと20年で日本のロータリーはどのように変わっていくのでしょう?
今後の私のテーマは「海外との交流で培われたさまざまな能力を活かして、ロータリー活動を一般向けに広報し、ロータリーの公共イメージのアップを行い、日本のロータリークラブ全体の活性化につなげる」です。それが職業奉仕なのか、社会奉仕なのか、私にはわかりませんが、私のやりたいことです。