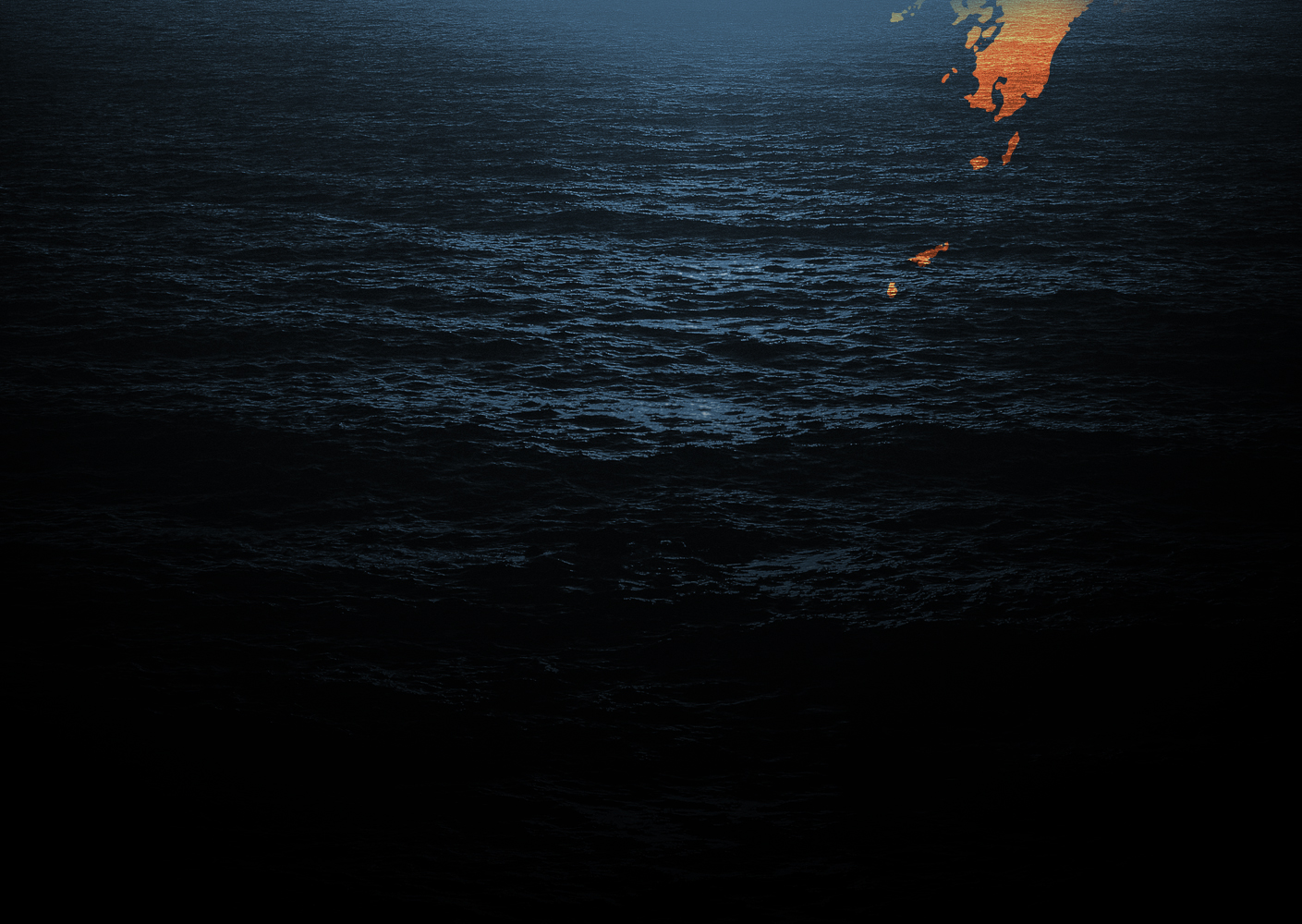「例会」にご参加いただき、感想をお寄せください。
ロータリーに関する資料を集めてみました。参考にしてください。
ロータリー資料室ロータリークラブは原則一人一業種で選ばれた良質の職業人が、毎週一回定例の会合に集い、例会を通じて奉仕の心を育み、自らの職業倫理を高め、その心を持って職場や地域社会・国際社会で奉仕活動の実践をすることにあります。
| 14-15年度RIテーマ | ロータリーに輝きを |
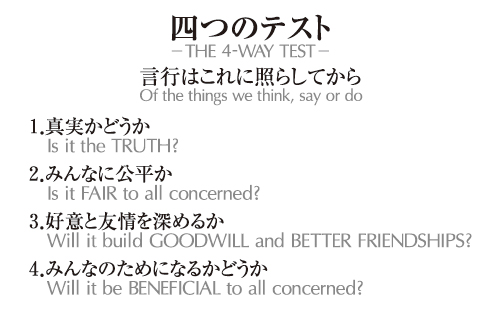
新「ロータリーの目的」
ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励し、これを育むことにある。具体的には、次の各項を奨励することにある。
1.知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること。
2.職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事は全て価値あるものと認識し、社会に奉仕する機会としてロータリアン各自の職業を高潔なものにすること。
3.ロータリアン一人一人が、個人として、また事業および社会生活において、日々、奉仕の理念を実践すること。
4.奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネットワークを通じて、国際理解、親善、平和を推進すること。
付記
「ロータリーの目的」の4つの項目は、等しく重要な意味を持ち、また同時に行動をおこさなければならないものであるということで、RI理事会の意見が一致した(ロータリー章典26.020)
1.奉仕の理想
奉仕の理想に 集いし友よ
御国に捧げん 我等の生業
望むは世界の 久遠の平和
めぐる歯車 いや輝きて
永久に栄えよ
我等のロータリー ロータリー
2.それでこそロータリー
どこで会っても やあと言おうよ
見つけた時にゃ おいと呼ぼうよ
遠い時には 手を振り合おうよ
それでこそ ローロー ロータリー
3.手に手つないで
手に手つないで つくる友の輪
輪に輪つないで つくる友垣
手に手 輪に輪 ひろがれまわれ
一つ心に おおロータリアン
おおロータリアン
4.ありがとうロータリー
富士の高嶺みつめて 地に足を踏みしめ
喜びと誇りを胸に 今もこれからも
ありがとうロータリー
出逢えた奇跡 奉仕の理想に向かって
ありがとうロータリー
分かち合うしあわせ
共に歩もう 未来をみつめて
それぞれのなりわいを それぞれの方法で
歩んできた だから今 新しい道がある
ありがとうロータリー
出逢えた奇跡 奉仕の喜びに向かって
ありがとうロータリー
分かち合うしあわせ
共に歩もう 未来をみつめて
ありがとうロータリー
出逢えた奇跡 奉仕の理想に向かって
ありがとうロータリー
分かち合うしあわせ
共に歩もう 未来をみつめて
会長:東 岳也
みなさん、こんにちは。2730ジャパンカレントロータリーEクラブ第33回例会を開催いたします。
さて、桐明会長エレクトが会長研修セミナー(PETS)を受講され、今週の例会で報告がなされています。そして、幹事報告では野中ガバナーエレクト事務所から届いた5月24日に延岡市で開催される地区研修・協議会について案内がなされております。
この地区研修・協議会(District Training Assembly)(DTA)は、3月~5月のいずれかの月に開催されることが望まれており、1日セミナーの目的は以下のとおりとされております。
・次期クラブ指導者が任期に備えて準備を整え、指導者チームを築くこと。
・クラブ指導者チームの意欲を高め、協力関係を築くための機会を、地区ガバナーエレクトと次期ガナバー補佐、および地区委員会に提供すること。
となっております。
詳細は後日メールにて各会員に案内がありますので、可能な限り参加いただけたらと思います。
また、現在奉仕プロジェクト委員会から6月7日に宮崎イオンで第2回ポリオ撲滅街頭募金活動について承認され今後計画を具体化されていきます。私たちのクラブにとって2回目のプロジェクトになります。委員会の皆さんを中心に会員の皆様の協力をお願いします。
今後、年度末に向け、様々な研修会やプロジェクトが多くなってきますが、機会をみつけご参加いただきますようよろしくお願いします。
|
会員数
|
出席義務
会員数
|
出 席
会員数
|
出席免除
会員数
|
出席率 |
|
25
|
25
|
24
|
0 |
96.00%
|
|
会員数
|
出席義務
会員数
|
出 席
会員数
|
出席免除
会員数
|
出席率
|
| 25 | 25 | 23 | 0 | 92.00% |
|
会員数
|
出席義務
会員数
|
出 席
会員数
|
出席免除
会員数
|
出席率 |
| 25 | 25 | 21 | 0 | 84.00% |
| 佐々木 慈舟さん (都城RC) | 落合 雅子さん (宮崎北RC) | ||
| 中山 信彦さん (志布志みなとRC) | 塩月 隆久さん(延岡東RC) | ||
| 榎木田 智子さん(宮崎西RC) |
2730地区の会長エレクト研修セミナー(PETS)が3月7・8の両日、延岡市のホテルで開かれ、参加して参りました。セミナーには地区内65クラブの会長エレクトが出席し、野中玄雄ガバナーエレクトや安満良明RI第3ゾーンコーディネーターをはじめ地区の各部門長などから2日間にわたって、みっちり研修を受けてきました。
まず、野中ガバナーエレクトからは、K.R.ラビンドラン次年度RI会長が提唱されている次年度のRIテーマ「世界へのプレゼントになろう」について、お話がありました。このテーマについてのラビンドラン次年度会長のコメントは菊地平研修リーダーが先の例会で分かりやすく紹介されていますので詳しくは述べませんが、要は、人は才能、知識、能力、努力、そして献身と熱意など、誰でも与えることのできる何かをもっているはずである。これらは「天からの授かりもの」であり、そのお返しをしましょうということです。
原文では「Be a Gift to the World」で、ギフトとなっています。英語では同じ贈り物でもプレゼントよりギフトの方が、格が上だそうですが、日本ではギフト券などの使われ方もあり、むしろプレゼントの方がふさわしいということになったそうです。
さて、このRIテーマを次年度の活動にどう生かしていくか、それにはまずテーマにある「世界」をどう想定するかが問題です。野中ガバナーエレクトからは、その世界は例えば職場であり、地域であり、家庭であってもいい。また、プレゼントも奉仕と換言してもよい、という説明がありました。
さらに、野中ガバナーエレクトは、RIテーマの実現に向け、その方向をより明確にするため「奉仕は力!活かそう例会」という2730地区のモットー(サブテーマ)を設定されました。その意味するところは、他者への奉仕(利他)が結局は自分自身への活力となり、発展をもたらすとの理念を「奉仕の力」と表現したものであり、「活かそう例会」は活気ある例会の実現を目指すもので、喜んで出席したくなるような楽しい例会を工夫していこうということです。
安満第3ゾーンコーディネーターからは、会員基盤の充実と増強、人道的支援の重点化と増加、ロータリーの認知度の向上などについて、お話がありました。特に、会員増強については新会員候補の推薦と退会防止を同時に進めることが大切だということです。また、クラブとして戦略的な長期計画を立て、目標を達成するためには会長と直前会長、会長エレクトの連携が重要である、と強調されました。
研修2日目、我がEクラブの特別代表であるパストガバナー、長峯基次年度地区研修リーダーには講評の中でEクラブのPRをしていただき、特にEクラブでのメークアップのやり方について「各クラブで若い人をリーダーとしてEクラブの活用法を考える取り組みをしてほしい」と、提案されました。
なお、ラビンドラン次年度RI会長については「ロータリーの友」3月号に特集が組まれています。また、ロータリー特別月間が次年度から大きく変更されますが、「ロータリーの友」2月号に紹介されていますので、お目通しを願います。
これから次年度に向けての準備が始まります。5月24日には延岡市で地区研修協議会が開かれます。各委員長をはじめ、できるだけ多くの会員にご参加いただければと思います。よろしくお願いします。
 |
 |
| 研修の様子 | 宮崎県西部分区協議 |
今月は識字率向上月間ですから、このことについて触れてみます。
今の私たちには考えられないことですが、現在、世界の子供たちで学校教育を満足に受けられない数が余りに多いのに驚かされます。
RIの国際識字年の目標は2015年までに世界の子供が漏れなく初等教育をうけられるようにすることを目指していました。国連によりますと、読み書きの出来ない人は世界に20億人いると言います。実に世界で3人に1人は貧困から抜け道が無いに等しいということです。それはまた、地球人口の3分の1の人が本や新聞や雑誌を読むという素朴な喜びから締め出されているということなのです。
そのために、このような病院では、職員が洗浄剤のラベルを読み間違えるために、危険なことが日常的に起こっていて、珍しいことではないということです。
今、サハラ以南のアフリカなど、第3世界を中心に世界中で学童期にある子供の内、1億2,500万人が全く学校に通っておらず、さらに。1億5,000万人は基本的な読み書きが出来ないうちに学校から離れてしまっている環境にいるといわれています。
難民救済の支援活動をされている、曾野綾子さんが、かつて、こう話されていました。「支援活動に鉛筆を沢山頂きますが、エンピツを削るナイフが無いのです。ボールペンの方がはるかに有効なのです」と。非識字と貧困は悲惨な悪循環を生み出しているのだと思います。
RIの目標達成には、世界で年間80億ドルの教育予算が必要とされていますが、この年間80億ドルという金額は、世界の軍事費のたった4日分と言われています。
ノーベル平和賞受賞のマララさんが「なぜ戦車をつくることは簡単で、学校を作ることは何故難しいのか?」と訴えたことを思います。
ここ日本にあって、つくづく平和の有難さを思うと同時に、平和への願いを祈らずにはいられません。
我が国の識字率の歴史を見ますと740年頃、天平の頃で、大化の改新終り、壬申の乱静まり、古事記が書かれた頃です。字の書ける人は京で1戸に1人いたそうです。全国では郡司の役所に勤めている者だけで、庶民は読み書きが出来なかったといわれています。「三下り半」という言葉があります、夫から妻、または妻の父兄宛に当てた離縁申し渡し状を三行半で書く慣わしであったことから来ています。一般には字が読み書き出来なかったので三行半の棒線を書くことから、三下り半といわれたわけです。
ヨーロッパでもフランス革命の頃、結婚の署名の出来たのは三分の一ぐらいの男女だったといわれています。
日本の約400年前、豊臣秀吉の頃、島津藩によって朝鮮から連れてこられた30人余りの陶工の人は、ほとんどの人が字を書けて、その事によって日記が残って歴史を伝えています。識字とは大変な文化なのです。
世界の識字率のテーマは、水保全問題とともに、ポリオに次ぐRIの重要なプログラムであることを、承知しましょう。
私がガバナーエレクトとして、アナハイムの国際協議会での研修期間中のことです。「終日ボランティアをしていただきます」との指示があり、世界から集まった 500人のエレクトはジャンパー姿になり、フードバンクと言う大倉庫に移動しました。そこには食料品が山済みされていました。その食料品がコンベアで流れてきます、それを、ロータリーマークの袋に一心に汗して入れる作業でした。
~多分世界の飢餓に苦しむ人達の一時の癒しになったでしょうか?
500人の夫人たちは前もって送っておいた子供向けの本を一冊ずつ、ロータリーマークのシールを貼っての箱積め作業でした。
その日の昼食は、コッペパン1個と小さな缶ジュース1個だけの粗食でした。
それによって「浮かされた昼食費が財団に寄付される」というボランティア研修を経験しましたが。日本語の子供本は何処の国へ配布されたのでしょうか?
絵本が主でしたから、きっと世界の、恵まれない、字の読めない子供達には貴重なプレゼントになったと思います。
復帰。理事会は、その懇願がありクラブに対する同人すべての負債が完済されれば元会員を会員身分に復帰させることができる。しかしながら、同人ぼ以前の職業分類が本定款の第8条第2節に適っていない場合は、いかなる会員も正会員に復帰させることはできないことを知っていましたか?
(2730ジャパンカレントロータリーEクラブ定款第12条3節 ―終結―会費不払(b))
Q1)今回の「委員会報告」についてご感想をお書き下さい/
Q2)今回の「メインプログラム」についてご感想をお書き下さい/